【2025年4月】省エネ基準義務化で住宅価格は激変?高値売却のポイント
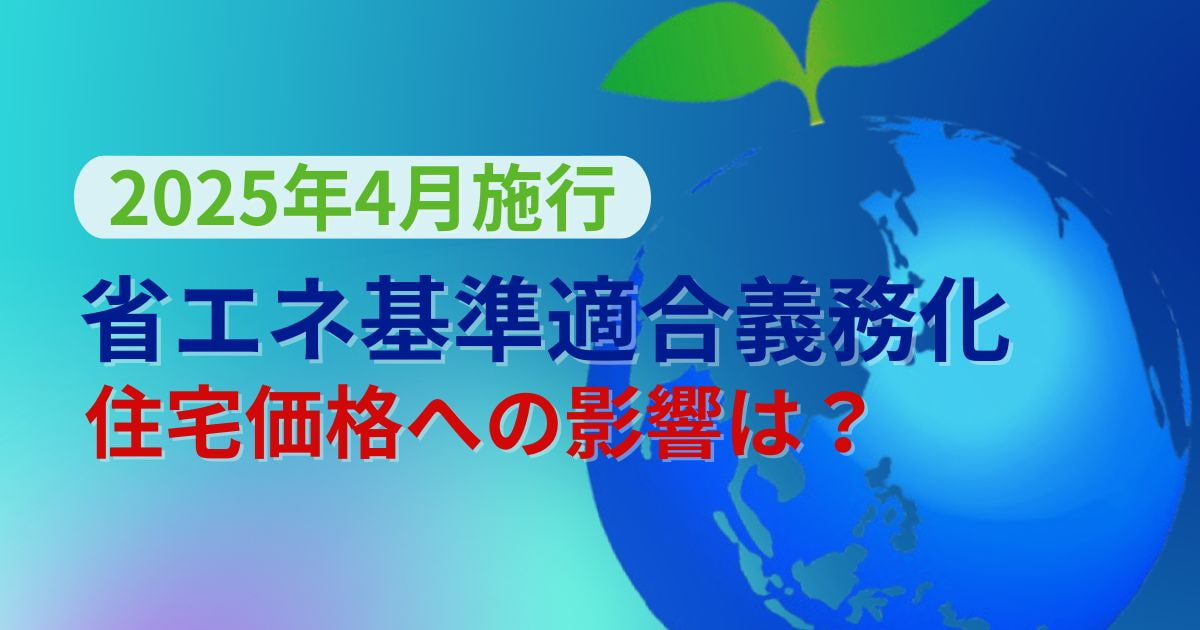
2025年4月から住宅の省エネ基準適合義務化により、新築住宅の性能向上が求められる一方で、中古住宅市場にも影響が及ぶおそれがあります。
「義務化で住宅価格はどう変わるのか」「いま家を売るべきか」こうした疑問を持つ方も多いでしょう。
省エネ基準義務化のポイントと、住宅価格に与える影響をわかりやすく解説します。さらに、高値で売却するための具体的な戦略についても紹介します。
もくじ [非表示]
2025年4月施行の省エネ基準適合義務化とは?
2025年4月から、新築住宅に対する省エネ基準適合が義務化されます。これまで努力目標とされていた基準が、300平方メートル未満の住宅も含め、すべての新築住宅に適用されます。(参考:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」)
この義務化によって、住宅の断熱性能やエネルギー効率が向上し、より快適な住環境の実現が期待されています。その一方で新築住宅の価格上昇や、省エネ基準を満たさない中古住宅の市場価値への影響も懸念されています。
ここでは、施行前の省エネ基準と義務化後の変化について解説します。
義務化前の省エネ基準はどうだった?
これまで、新築住宅の省エネ基準は建築主の判断に委ねられており、義務ではありませんでした。
2013年の改正により、住宅の一次エネルギー消費量の基準は定められていましたが、あくまでも「努力目標」とされていたのです。
なお、一次エネルギー消費量は、次の設備で消費されるエネルギーの合計から算出します。
- 空調・暖冷房設備
- 換気設備
- 照明設備
- 給湯設備
- 昇降機
- 事務機器・家電調理など
しかし、一次エネルギー消費量の基準値を超えても建築主や購入者に、ペナルティーはありませんでした。そのため、省エネ性能が低い住宅が多く建設され、実際に基準を満たしている住宅は限られていたのです。
また、これまでは住宅の性能にかかわらず、住宅ローン減税の対象となっていたため、購入者は性能よりも価格を重視する傾向がありました。その結果、省エネ基準を満たしていない住宅が多く流通しましたが、2025年4月の義務化によって状況が大きく変わります。
2025年4月以降に変わるポイント
2025年4月から、新築住宅の省エネ基準適合が義務化されます。これにより、住宅の断熱性やエネルギー消費に関する基準が強化され、新築住宅には一定の省エネ性能が求められます。
義務化による主な変更点は以下の4つです。
- 対象範囲の拡大
- 断熱性能の強化
- 一次エネルギー消費量の削減
- 住宅ローン減税への影響
これまで努力義務にとどまっていた300平方メートル未満の住宅を含め、すべての新築住宅が適用対象となります。また、断熱性能の基準が強化され、今後は住宅の断熱性が向上するでしょう。
なお、断熱性能はUA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)によって等級が決まり、低いほうの等級が適用されます。等級4以上が省エネ基準を満たすレベル、等級5以上で高性能な省エネ住宅と認定されます。(参考:国土交通省「断熱性能」)
また、一次エネルギー消費量の削減についても、☆表記で評価が記載され、省エネ基準は0%以上で達成とされ、20%以上の削減は誘導基準とされています。(参考:国土交通省「エネルギー消費性能」
今後、省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン減税の対象外となるおそれがあるため注意が必要です。
この義務化により、新築住宅の省エネ性能が向上し、光熱費の削減や快適な住環境の実現が期待されます。しかし、基準を満たさない中古住宅の市場価値が低下する可能性もあり、今後の売却について考慮する必要があるでしょう。
なお、中古住宅にはリフォームなどの義務はありませんが、改修を行わない限り、省エネ基準に適合しないままです。これにより、省エネ性能の低い物件は市場で敬遠されるリスクが高く、売却価格にも影響を与えることが考えられます。
省エネ基準適合義務化で住宅価格はどう変わる?
2025年4月の省エネ基準適合義務化によって、新築住宅と中古住宅の価格は大きく変化するといえるでしょう。新築住宅は、省エネ性能を高めるための追加コストにより価格が上昇すると予想されています。
一方で、省エネ性能が低い中古住宅は、今後の市場で敬遠されるリスクがあり、売却価格が下がることが懸念されます。ここでは、義務化による住宅価格の変動について詳しく解説します。
義務化前に購入した中古住宅、そのまま売ると価格は下がる?
省エネ基準の義務化により、断熱性能が低い中古住宅の需要は低下すると考えられます。ただし、義務化直後に急激に価格が下がるわけではなく、徐々に市場の変化を受けて影響が出てくる見込みです。
今後、省エネ性能の低い中古住宅の価格が下がると考えられる要因は次のとおりです。
- 省エネ性能が低い住宅は、住宅ローン減税の対象外となるおそれがある
- 買主が省エネリフォームの費用を考慮し、価格交渉を行うケースが増える
- 光熱費の上昇を背景に、省エネ性能の高い住宅の需要が拡大
例えば、買主が住宅ローン減税の適用を希望する場合、省エネ基準を満たすためにリフォームが必要です。仮にリフォーム費用が500万円かかる場合、売主は当初1,500万円で売り出していた住宅を、買主の要望に応じて1,000万円に値下げせざるを得ないこともあるでしょう。
新築住宅価格は上がる?
新築住宅の価格は、省エネ基準の義務化により上昇する可能性が高いと考えられます。特に、以下の要因がコスト増加につながります。
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 断熱性能向上 | 高性能断熱材の使用によりコスト増加 |
| 一次エネルギー消費量削減 | 高性能設備の導入で費用増 |
| 人件費 | 残業規制による施工コスト増加 |
| 資材費 | 断熱材や窓の価格自体が高騰 |
これらの要因により、新築住宅の価格は100〜300万円程度上がると見込まれています。
一方で、省エネ性能が向上することで光熱費が削減され、住みやすさが向上するというメリットもあります。そのため、長期的な視点で見れば、省エネ基準に適合した住宅の需要は今後ますます高まるでしょう。
義務化前に購入した中古住宅は、リフォーム後のほうが高値で売れる?
中古住宅は、省エネリフォームを行うことで売却しやすくなりますが、リフォーム費用がそのまま売却価格に反映されるとは限りません。
一方、以下のような部分的なリフォームは、中古住宅の売却に有利になることもあります。
しかし、500万円以上かかるフルリフォームを行っても、その分が売却価格に上乗せできるとは限らないため、慎重な判断が必要です。
むしろ、買主が自分でリフォームしたいと考えるケースもあるため、全面改修よりも部分的なリフォームのほうが売却しやすい傾向があります。
また、リフォーム費用をそのまま販売価格に上乗せするのではなく、割り引くことで購入希望者にとって魅力的な価格設定になるでしょう。窓の交換や断熱材の施工、省エネ型給湯器の導入などは、補助金を活用できる場合があり、低コストでリフォームを行うことが可能です。
義務化後の住宅市場では、省エネ性能が住宅の価値を大きく左右するため、売却前にどのような対策を取るかが重要になるでしょう。
義務化に伴い、早めに売却したほうがよい住宅の特徴
2025年4月の省エネ基準適合義務化により、省エネ性能の低い住宅は市場での評価が下がるおそれがあります。特に築年数が古く断熱性能が低い住宅や、耐震性が不十分な住宅は、売却の際に価格が下がることが予想されます。
ここでは、義務化の影響を受けやすい住宅の特徴について詳しく解説します。
築30年以上で省エネ基準を満たさない物件
1999年以前に建てられた住宅の多くは、現在の省エネ基準を満たしていません。特に、当時の断熱性能に関する規制は緩く、使用される建材や施工方法も現在と比べ断熱性の低いものが一般的でした。そのため冬は寒く、夏は暑いといった快適性の低さが課題となります。
また、省エネ性能の低い住宅は、住宅ローン減税の対象外となるおそれがあり、買主にとってのメリットが少なくなります。これにより、今後の市場では省エネ性能の高い住宅が標準化し、基準を満たさない住宅の需要は減少すると考えられます。
築30年以上の中古住宅の売却を検討している場合は、市場価値が下がる前に売却を進めるか、省エネリフォームを施すことで、より有利な条件で売却できる可能性が高いでしょう。
断熱性能が低い&冷暖房コストが高い物件
断熱性能が低い住宅は冷暖房の効率が悪く、年間の光熱費が高くなりやすいため、買主に敬遠される傾向があります。特に、単板ガラスの窓や断熱材がほとんど入っていない住宅は、外気の影響を受けやすく、エアコンや暖房を長時間使用しなければ快適な室温を維持できません。
このような住宅は、そのままの状態では売却価格が下がる可能性があります。しかし、「窓を二重ガラスに交換する」「壁や床に断熱材を追加する」などの対策を行うことで、冷暖房効率が向上し、年間の光熱費を数万円単位で削減につながります。
ただし、リフォームには費用がかかるため、売却前にどの程度の改修を行うか慎重に検討することが大切です。
例えば、1,000万円の住宅を200万円かけてリフォームした場合、1,200万円で売却できるのが理想です。しかし、あえてリフォーム費用を割り引いて1,100万円で売り出すことで、買主の関心が高まり、売却をスムーズに進められることもあります。
旧耐震の住宅
1981年以前に建てられた住宅は、現行の耐震基準を満たしていない「旧耐震」の住宅に分類されます。耐震性が不十分な住宅は、地震による被害リスクが高く、購入希望者にとって不安要素となるため、市場価値が低下しやすい特徴があります。
また、旧耐震の住宅は住宅ローン減税や補助制度の対象外となるケースが多いため、買主にとってのメリットが少なくなります。そのため、購入希望者が現れにくく、売却が難しくなる傾向にあります。
耐震補強工事を行うことで安全性が向上し、住宅ローン控除の適用を受けられる場合もありますが、補強には200万円程度の費用がかかることが一般的です。
そのため、リフォームを実施するか、そのままの状態で売却するかは、費用対効果を考慮する必要があります。
築年数が古く、耐震性が不安視される住宅を売却する場合は、購入希望者にとってのリスクを軽減するため、「耐震診断を受ける」「補助制度を活用する」などの方法を検討するのも有効です。
中古住宅を高く売るための注意点
中古住宅をスムーズに売却するには、事前に戦略を立てることが重要です。特に、省エネ基準の強化により、住宅の性能が価格に与える影響はこれまで以上に大きくなります。
ここでは、中古住宅をできるだけ高く売るためのポイントについて解説します。
補助制度を活用する
省エネ基準の義務化に伴い、中古住宅の断熱改修や省エネ設備の導入がより重視されます。これらの改修にはコストがかかりますが、国や地方公共団体(自治体)の補助制度を活用することで、自己負担を抑えて省エネ性能を向上させることが可能です。
例えば、2024年に実施された「子育てエコホーム支援事業」では、壁や窓の断熱改修や高効率給湯器の設置に対し、20〜60万円の補助が受けられました。また、「先進的窓リノベ2024事業」では、窓の二重ガラス化や断熱材の施工に対し、最大200万円の補助が適用されていました。
補助制度を活用することで断熱性能を高め、省エネ設備を導入し、光熱費を削減するだけでなく、売却時に「省エネ住宅」としてアピールできます。省エネ改修を施した住宅は市場での評価が高まり、売却価格アップにもつながるでしょう。
2025年3月下旬からは、「子育てグリーン住宅支援事業」申請開始が予定されています。補助制度は適用条件や申請期間が定められているため、早めにリフォームを検討し、工務店や専門家に相談することが重要です。
省エネ基準の強化に備え、2030年までに売却またはリフォームを
2025年の省エネ基準適合義務化に続き、2030年にはさらなる基準強化が予定されています。これにより、省エネ性能の低い住宅の市場価値はさらに低下するおそれがあります。
2025年時点では、断熱等級4が省エネ基準として求められますが、2030年にはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベルの断熱等級5〜6が標準になる見込みです。
今後、省エネ基準が厳しくなることで、特に2030年以降は「省エネ性能が低い住宅」として評価が下がるリスクが高いでしょう。そのため、築年数が経過した住宅は、できるだけ早めに売却するか、リフォームで価値を高めることが重要です。
また、断熱改修などで住宅性能を高めることで、買主が住宅ローン減税の適用を受けやすくなり、購入意欲が高まりやすくなります。自宅や実家などの売却を検討している場合は、2030年を見据えた計画を立てることがポイントです。
実績豊富な不動産会社、複数社に相談する
中古住宅の売却価格は市場の動向や物件の立地、特徴によって大きく変動します。さらに、省エネ基準の強化により、住宅の性能が価格に与える影響が大きくなるため、売却を検討する際は専門的な知識を持つ不動産会社に相談するのがおすすめです。
不動産会社によって、売却に強いエリアや物件の種類は異なります。また、査定基準や売却戦略も異なるため、1社だけでなく複数の会社に査定を依頼し、最適な売却方法を検討しましょう。
省エネ改修に関して知識がある不動産会社を選ぶことで、住宅を適正価格で売却できる可能性が高まります。
売却を成功させるためには、売買実績が豊富な不動産会社を選び、信頼できる会社と連携してタイミングを逃さず売却を進めることが大切です。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
離婚で家を財産分与 (26) 老後の住まい (22) 一括査定サイト (15) 売れないマンション (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 離婚と住宅ローン (11) 家の売却 (9) 不動産高く売る (8) マンション価格推移 (8) 実家売却 (8) マンションの相続 (8) 家の後悔 (8) 移住 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 空き家売却 (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) お金がない (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 近隣トラブル (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて

















