離婚後の養育費と住宅ローンを相殺・減額できる?支払いがキツいときはどうする?
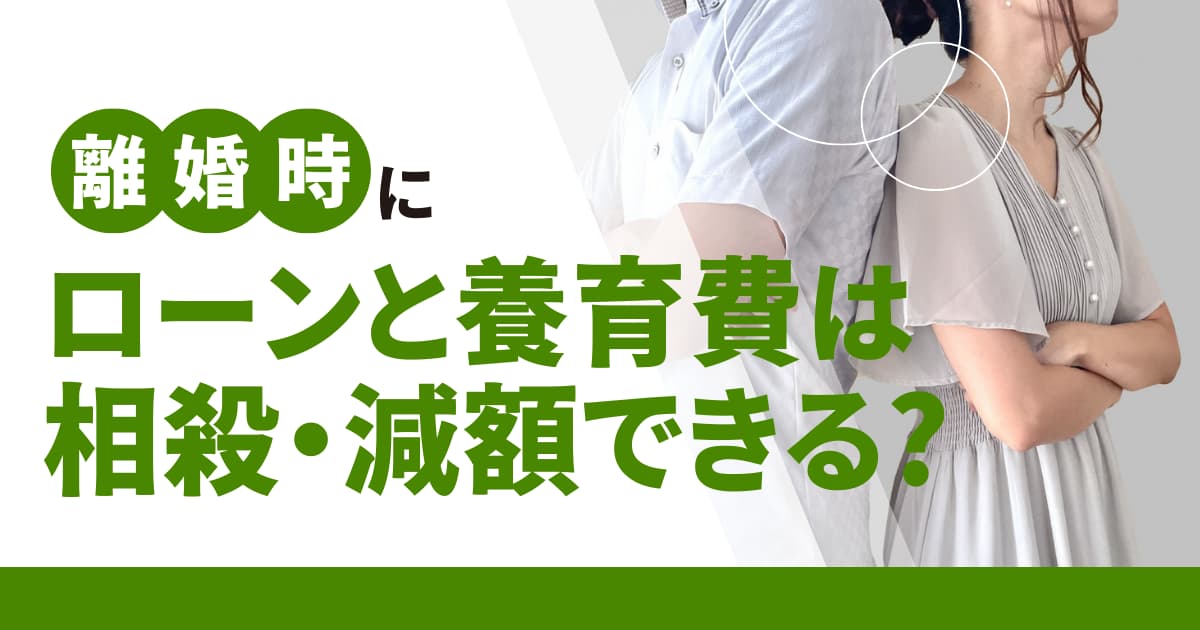
離婚をしたときに子どもがいると、親権を獲得した配偶者へ養育費の支払いが必要になります。住宅ローンの支払いもしている場合は、負担が重くのしかかってくるでしょう。
しかし、離婚時の財産分与の結果、住宅ローンの名義人ではない配偶者が住むこともあります。そうなった場合、養育費に対して住宅ローンで相殺したり、減額したりできるのでしょうか。離婚したときの養育費と住宅ローンの関係について、一括査定サイトの「リビンマッチ」がわかりやすく解説します。
知らないと危険!養育費の基本

離婚や別居をすると、子どもを育てる費用として親権を持つほうへ「養育費」の支払いが必要になります。しかし、具体的な金額や支払い期間、未払い時のリスクについて正しく理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。養育費の基本を見ていきましょう。
養育費はいくら払う?
養育費の金額は、親の収入や子どもの年齢、生活環境などを考慮して決定します。一般的には家庭裁判所が示す「養育費算定表」を参考にしながら決めることが多いですが、夫婦間の合意で調整することも可能です。たとえば、収入が高い親であれば相応の養育費を支払う必要がありますし、逆に収入が少ない場合は負担額が軽減されることもあります。
厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯が受け取っている養育費の平均月額は約50,485円、父子世帯では約26,992円となっています。また、最高裁判所の司法統計によると、父親が支払者となった場合の養育費の金額は、月額2万円超~4万円以下が約38.9%ともっとも多く、次いで1万円超~2万円以下が約32.6%となっています。これらのデータから、多くの親が月額2万円から4万円程度の養育費を支払っていることがわかります。
参考:厚生労働省「令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要(PDF)」
養育費はいつまで払う?
養育費は子どもが未成年の間だけ支払うようなイメージがあります。そのため、2022年の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたのですから、子どもが18歳になるまで支払えばよいのでしょうか。実は、養育費を支払う期間に定めはありません。
養育費は「こどもが自ら稼働して経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるべきもの」(引用:法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」)とされているため、未成年の間だけとは限らないのです。たとえば、子どもが成人していたとしても、大学在学中の生活費を稼ぐことは困難ですから、大学へ進学したら22歳まで支払う必要があると考えられます。そのため、養育費の支払い期間については、子どもの教育計画や進学希望を考慮し、事前にしっかり話し合っておくことが大切です。
参考:法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(PDF)」
養育費を払わないとどうなる?
養育費を支払わない場合は、法的措置が取られることがあります。まず、親権を持っているほうが家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。また、養育費の支払いが確定している場合には、給与の差し押さえなどの強制執行が行われることもあります。さらに、養育費の未払いは社会的信用にも影響を及ぼすため、長期間未払いを続けることは大きなリスクを伴います。
養育費は、子どもの健全な成長にとって欠かせないものです。適切な金額を決め、期限まで支払い続けることが親としての責任であることを理解し、計画的に対応しましょう。
養育費は住宅ローンで相殺・減額できる?

住宅ローンと養育費を相殺・減額できるかどうかは、ケースごとに結果が異なります。考えられるケースは以下の2パターンです。
- 住宅ローンの名義人が家に住む
- 名義人でない元・配偶者が家に住む
自身が当てはまる事例を確認し、離婚後の住宅ローンや養育費の支払いでトラブルにならないように、手続きなどを進めていきましょう。
住宅ローンの名義人が家に住む
住宅ローンを支払っている人(名義人)が養育費の支払い義務者でもあり、支払いの対象である持ち家に住む場合は、基本的に相殺・減額ができません。養育費の支払い義務者が、自分の生活に必要な生活費を住宅ローンとして支払っている形となり、養育費の支払いを受ける側にプラスとなる要素がないためです。養育費の支払額は、法律で金額が決められているわけではありませんが、裁判所が養育費の相場を「養育費・婚姻費用算定表」として公開しています。
養育費・婚姻費用算定表で確認するのは、養育費を支払う側と受け取る側の年収や、子どもの数・年齢などです。住宅ローンの支払者が養育費を支払う側でもあり、持ち家に住むという場合は、養育費・婚姻費用算定表から算出した相場を基準に、養育費の金額を決める流れになります。しかし、住宅ローンと養育費をどちらも払う形となり、支払い困難になるおそれもあるため、年収などを考慮したうえで「養育費が継続して支払える額なのか」という点を検討することが大切です。
名義人でない元・配偶者が家に住む
住宅ローンの名義人と養育費の支払い義務者が同じ、住宅ローンの名義人が家に居住せず、養育費の支払いを受ける側が家に住むなら、相殺・減額ができます。支払いを受ける側は、住宅ローンを支払ってもらうことで、自分や子どもが暮らす住居を確保されていますが、住宅ローンを支払う側は別に自身の家賃など居住にかかる費用が必要です。
もし住宅ローンの支払いが困難になった場合、持ち家を売却したり、権利が金融機関に移ったりすると、支払いを受ける側と子どもの住居が失われてしまいます。そのため、支払いを受ける側が持ち家に暮らしているのであれば、住宅ローンを支払っている点を養育費の額を決定する際に考慮することが、支払いを受ける側や子どものためにも必要です。相殺・減額の金額は一律で決められていませんが、主に以下の2つの方法があります。
- 養育費の相場を確認する際の「基礎年収」を計算するときに住宅ローンを考慮する
- 裁判所が公開する「養育費・婚姻費用算定表」から住宅ローンの額を差し引く
住宅ローンの完済まで、問題なく支払いを続けられるよう配慮して金額を決めていきましょう。
要注意!離婚時の住宅ローンと養育費のトラブル

住宅ローンと養育費に関して、以下のようなトラブルが起こりうるので、事前に対処法も合わせて内容を理解しておきましょう。
- 負担が大きくて支払いを滞納する
- 住宅ローンの契約に違反する
- 養育費の減額で住宅ローンの負担が重い
年収や子どもの人数・年齢のほか、離婚後の生活の変化などによっても起こるトラブルは異なります。さまざまな事例を確認して自分なりにシミュレーションをしておくことが大切です。
負担が大きくて支払いを滞納する
夫婦で助け合って住宅ローンや養育費を支払ってきたものを、ひとりでどちらも支払わなければいけない状態になると、負担が大きくなり、支払いができなくなってしまうおそれがあります。住宅ローンの支払いができないと起こるトラブルは、以下のとおりです。
- 保証人に支払いの請求がいく
- 抵当権により家が競売にかけられる
- 強制退去となり家を失ってしまう
一般的に夫が住宅ローンの名義人とのケースが多いですが、保証人や連帯保証人に妻を設定していると、支払いの滞納が発生した際に請求が保証人や連帯保証人である妻に請求がいきます。滞納が発生したときにトラブルが起きないよう、契約した金融機関と話し合って対処しておくことが大切です。
また、住宅ローンを契約した際には「支払いができない場合は、家を売却して補てんする」という抵当権の設定がされています。そのため、滞納が続くと最終的には自分の家でなくなり、強制退去となってしまいます。滞納が発生する前に、養育費などの負担が大きい場合は弁護士に相談しましょう。状況によっては、弁護士や支払いを受ける側との話し合いをもうけたうえで、金額の見直しをすることも可能です。
住宅ローンの契約に違反する
金融機関で異なりますが、住宅ローンの契約をする際には「対象となる家に暮らすこと」が条件となります。住宅ローンを支払っている契約者が、対象となる家に住んでいれば問題ありませんが、住まずに住宅ローンを支払っていく場合は契約違反となるおそれがあるため注意が必要です。
契約違反となると、住宅ローンの残債を一括で返済することを求められるなど、予想外のトラブルに巻き込まれるケースもあります。必ずしも一括返済を求められるとは限りませんが、離婚が成立する前や住居を移る前に金融機関に相談しましょう。
養育費の減額で住宅ローンの負担が重い
再婚や子どもの進学など、生活の変化によって養育費が減額される場合があります。夫婦それぞれで住宅ローンを支払うペアローンなら、養育費の減額によって自分の資金からも支払いが生じることもある点に注意しましょう。たとえば、これまで毎月10万円受け取り、住宅ローンに7万円、養育費に3万円使っていた場合、10万円が8万円に減ると、2万円分は自分の資金から支払わなければいけません。受け取る金額が減ってしまった場合でも、問題なく支払いを続けられるのか、事前に弁護士や支払う側と相談しておくことが大切です。
また「2025年までは毎月10万円支払うと約束したはず」など、口約束でのトラブルが起こる場合も多いので、トラブルを防ぐために公正証書を作成する方法もあります。裁判になった際には、公正証書が証拠として採用されるため、突然の養育費の減額などのトラブル回避に有効です。
養育費や住宅ローンの支払いがキツくなったら?

年収の変化や子どもの成長に伴って、住宅ローンや養育費の支払いが難しくなってしまうこともあります。「このまま支払いを続けるのは難しい」という状況になったら、以下の対処法を検討しましょう。
- 家を売却して負担を減らす
- 養育費の減額を要求する
- 住宅ローンの返済額・期間を変更する
住宅ローンの滞納などが発生すると、突然住居を失うなどのトラブルが起こりうるので、トラブルが起きる前に、弁護士や養育費を受け取っている側、金融機関などに相談しておくことが大切です。
住宅ローンの返済額・期間を変更する
家を売却した場合の額が、住宅ローンの残りの支払額よりも高い場合は、売却代金で住宅ローン完済が可能です。単独ローンであれば支払いをしている名義人、ペアローンであれば夫婦両方の承諾が必要になりますが、売却をすることで負担を大幅に減らせます。また、家を売却した場合の額が、住宅ローンの残りの支払額よりも低い場合でも、任意売却をすることで売却が可能です。
任意売却は、債権者の同意が必要になる売却方法で、通常売却と同じように一般市場に売りに出すことができます。住宅ローンを滞納してしまうと、債権者が競売にかけることになりますが、競売にかけるよりも任意売却で一般市場で売却をしたほうが金額が高くなる可能性あります。任意売却の経験が豊富で、専門的な知識がある不動産会社を探し、債権者である金融機関に事前相談をしたうえで手続きを進めていきましょう。
養育費の減額を相談する
離婚時の年収や子どもの年齢などによって養育費の額を決めますが、離婚後に生活の変化があった場合は、養育費の減額を要求できます。養育費を支払う側に、以下のような変化が起きた場合に要求が可能です。
- 収入が減った、なくなった
- 病気や怪我で働けなくなった
- 再婚をして子どもができた
とくに「収入の減少」は、養育費のほかに、住宅ローンや自身の生活費を支払えなくなってしまう重大な変化になるため、早めの相談が必要です。また、養育費を支払っている側が再婚をして子どもができた場合や、養子縁組をして育てるべき子どもができた場合などにおいても、今まで支払ってきた養育費の減額が可能です。養育費を決めたときと同様に、法律で金額が決められていないため、双方で話し合ったり、弁護士と相談したりしながら、どのくらいの金額とするのかを決めていく必要があります。
家を売却して住宅ローンを解消する
金融機関に相談して住宅ローンを契約した際に組んだ返済計画の見直しを行い、毎月の返済額や返済終了までの期間を変更することで短期的な負担を軽減できます。しかし、返済計画の見直しは必ず認められるわけではなく、審査に通った場合のみ見直しが可能です。また、毎月の返済額を減らすことで短期的な負担は減りますが、返済総額が今までよりも増えてしまうケースもあります。
返済期間が延びたことで、定年退職したあとも住宅ローンを支払わなければならないなど、新たな負担が増えてしまう場合もあるので注意しなければなりません。家の売却や養育費の減額など、ほかの選択肢も検討しながら、返済額・返済期間の見直しが最適なのかを金融機関などと相談してみましょう。
一括査定で持ち家の資産価値を調べる
持ち家の資産価値を調べるときは、不動産ポータルサイトなどから自分で相場を調べられますが、正確な価格を知りたいのであれば不動産会社の査定を受けたほうがよいでしょう。立地や間取りなどさまざまな要素から、正確な資産価値を把握できます。
不動産会社の査定も、できれば複数社に依頼することをおすすめします。各社の査定価格を比較すれば、より正確な価格がわかります。一括査定サイトの「リビンマッチ」であれば、一度の入力で複数の不動産会社へ査定を依頼できます。申し込みは24時間いつでもできますので、忙しい人でもご利用可能です。信頼できる不動産会社が見つかったら、売却までの手厚いサポートを期待できるでしょう。
関連記事

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
離婚で家を財産分与 (26) 老後の住まい (22) 一括査定サイト (15) 売れないマンション (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 離婚と住宅ローン (11) 家の売却 (9) 不動産高く売る (8) マンション価格推移 (8) 実家売却 (8) マンションの相続 (8) 家の後悔 (8) 移住 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 空き家売却 (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) お金がない (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 近隣トラブル (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて











